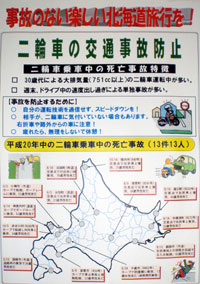| 83)元旦宗谷岬ツーリング2010(その三)_41) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 風も無く穏やかな雪中キャンプ日和に恵まれました。 2009年の大晦日は大荒れ予報に反して好天のツーリング日和になりました。それは過去の気象情報の積み重ねが未来に通用しなくなってきている現れかもしれません。予想外の好天もあれば予想外の悪天もある訳で、この時期の悪天候は交通環境を直撃します。 猛吹雪による視程不良や積雪による交通障害などの単純な事から、濡れた路面が部分的に凍結するブラックアイスバーンの罠まで様々な危険が存在します。冬のバイクに限らす冬の交通環境は危険が増大します、それは鉄道も例外ではありません。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 安全対策 | |||||||||||||||||||||
| 「安全運転」「安全運転」と何度呪文を唱えても「効果はありません」現場の実情に合った具体的な安全対策をしなければ安全は手に入らない。 それも100%の安全など存在しない、もしそれを実現するなら家でソファーに寝そべってテレビを見ている事だ(笑) 安全に近付くには「安全」か「危険」という漠然とした捉え方では無く、「具体的な危険」を一つ一つ分析して、それぞれに一つ一つ「対策」をして、その対策の集合体をもって全体の安全率を上げていく、もしくは事故に遭う確立を減らしていく。それ以外に道は無い。 「安全対策」を練るには「具体的な危険」を判っている事が前提になる。北海道に暮らす人は、冬道の具体的な危険を知っている。それに照らして考えるから「北海道のバイク乗りは、冬にバイクに乗る事をしない」ものだ、その怖さを知らない本州の人々が、たまに真冬の北海道に夏タイヤのバイクでやってきたりする。 |
|||||||||||||||||||||
| 下の夏タイヤのバイクは1990年代の元旦宗谷岬の写真です。 | |||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||
| 元旦の宗谷岬に集ったスパイクを履いた完全装備のオフロードバイクの中に、ポツンと佇む場違いな夏タイヤの原動機付自転車。破れたサイドバックが散々転倒している事を物語っている。 | 夏タイヤの原動機付自転車を過積載にして足を垂らして走っていく。操縦安定性など望むべくもない。何かあってブレーキを掛けたら、その瞬間スリップ転倒、有無を言わせず路面を滑走する事になる。 | ||||||||||||||||||||
| 正直な話、夏タイヤで雪道を走れる場合もあります。 ただし、それは 「他の交通が無い場所で」 という絶対条件が付きます。 |
|||||||||||||||||||||
 |
左の写真は1995年に大怪我をして手術を受けてリハビリ中に、バイクのリハビリ用に買ったホンダの「V45マグナ」という750ccの大型バイクで林道を走りに行った時のもの、山奥では既に雪が積もっており、面白がって遊んだものです。 実は砂利道の初積雪はオンロード用夏タイヤでも楽しく遊べる場合があります。 重心を真っ直ぐに慎重に扱う。オフロードバイクの基礎があれば、路面状態次第で、それなりに走れて(遊べて)しまいます。(両足着地微速移動) |
||||||||||||||||||||
| ※逆に舗装路面では数センチ積もるか凍結すれば即「アウト」 | |||||||||||||||||||||
| 「冬のバイクはタイヤが命」 | |||||||||||||||||||||
| 宗谷岬にバイクで年越しにやってくる連中はその厳しさを知った上で、それに打ち勝つ装備を携えてやってくる。2010年元旦の宗谷岬に集ったバイク達の足元参考画像 | |||||||||||||||||||||
| 250ccオフロードバイクのタイヤ。かなりの悪条件でも交通の流れに乗って走る事が出来る性能をもっている | 110ccの原動機付き自転車のタイヤ。ピン数も十分で圧雪アイスバーンを安全に走れるタイヤ | ||||||||||||||||||||
| 50ccの原動機付き自転車のタイヤ。小さいながら接地面に集中的にピンを配置している。荒れた積雪路は厳しいが、締まった圧雪アイスバーンには侮れない威力を発揮する。 | 自転車ツーリストのタイヤ。走行抵抗とグリップ力のバランスのとれた自転車先進国北欧製のスパイクタイヤ | ||||||||||||||||||||
| 50ccのスーパーカブのタイヤ。耐久性重視で作られたベストセラーの冬タイヤ、先を急がない堅実な走り向き | 50ccのスーパーカブのタイヤ。強力なマカロニピンを増しピンして悪条件に強化した改造タイヤ、低圧で使用出来るようにビートストッパーも装備している。 | ||||||||||||||||||||
| ※ネジ項削除 | |||||||||||||||||||||
| おまけ | |||||||||||||||||||||
| もしどうしても急場を凌がなければならない状況になった場合は、下のオフロードバイクのように細めのタッピングスクリューをタイヤコード手前まで捻じ込んで頭をボルトクリッパーで落として尖らせるという方法で即席冬タイヤを作ると「夏タイヤ」のままよりはずっと「まし」になります。 ボルトの頭を飛ばして接触面積を小さくする事で、面圧が上がり氷雪に食い込むようになります。反面舗装路面上ではすごい勢いで磨り減ってしまいます。 この方法が出来るのはオフロードバイクの厚みのある丈夫なブロックタイヤに限ります。 |
|||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||
| 1990年代中ほどの元旦宗谷岬の写真 | |||||||||||||||||||||
| 本来のボルトピンスパイクはタイヤに貫通穴を開けて大き目のワッシャーを挟んでボルトナットで締め上げて、チューブに傷が付かないようにタイヤ内側のボルトの頭を透明なシリコンシーラーでコーティングして、タイヤトレッドに飛び出したボルトの先端をグラインダーで削って針のように尖らせます。 それは公道を走る為のものでは無く、アイスレースといって凍った湖の上で行う氷上レースに使う専用タイヤです。 ・・・かつてそんなタイヤを履いて宗谷岬に来ていたバイクもありました(笑) |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||